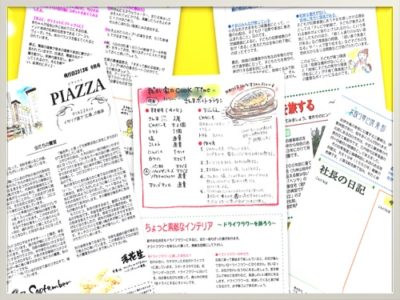知恩院

知恩院は、京都市東山区林下町にある浄土宗の総本山の寺院です。
山号は華頂山です。
本尊は法然上人像(御影堂)および阿弥陀如来像(阿弥陀堂)です。
開山は法然で、詳名は「華頂山知恩教院大谷寺(かちょうざん ちおんきょういん おおたにでら)」といいます。
 法然上人像
法然上人像
 阿弥陀如来像
阿弥陀如来像
知恩院の境内には、国宝の御影堂や三門、重要文化財の勢至堂、集会堂、大方丈、小方丈、経蔵、唐門、大鐘楼などの文化財指定建造物が建ち並びます。
このうち三門は、1621(元和七)年に徳川秀忠によって建立された日本最大級の木造二重門です。
こちらが知恩院で最も有名な建物とされています。
 三門
三門
 集会堂
集会堂
 唐門
唐門
 大鐘楼
大鐘楼
法然上人の像(御影)を安置する御影堂は、1639(寛永16)年に再建された中心的堂宇で、2020(令和2)年4月に、約9年間にわたる半解体修理が完了しました。
紙本著色法然上人絵伝(四十八巻)、絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図、上宮聖徳法王帝説(いずれも国宝)など多数の文化財を蔵しています。
 御影堂
御影堂
知恩院は浄土宗の宗祖・法然房源空(法然)が後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院です。
法然が東山吉水(よしみず)、現在の知恩院勢至堂付近に営んだ草庵をその起源とします。
現在のような大規模な伽藍が建立されたのは、江戸時代以降です。
徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、今も京都の人々からは親しみを込めて「ちよいんさん」「ちおいんさん」と呼ばれています。
法然は平安時代末期の1133(長承2)年、美作国(現・岡山県)に生まれました。
13歳で比叡山に上り、15歳で僧・源光のもとで得度(出家)します。
18歳で比叡山でも奥深い山中にある西塔黒谷の叡空に師事し、源光と叡空の名前の1字ずつを取って法然房源空と改名しました。
法然は唐時代の高僧・善導の著作『観経疏』を読んで「専修念仏」の思想に開眼し、浄土宗の開宗を決意して比叡山を下りました。
1175(承安5)年、43歳の時でした。
法然は東山の吉水に吉水草庵(吉水中房、現・知恩院御影堂、もしくは現・安養寺)を建てると、そこに入りました。
「専修念仏」とは、いかなる者も、一心に阿弥陀仏(阿弥陀如来)の名を唱えれば極楽往生できるとする思想のことです。
この思想はいわゆる旧仏教側から激しく糾弾され、攻撃の的となりました。
法然は1207(建永2)年の承元の法難で讃岐国(現・香川県)に流罪となりましたが、4年後の1211(建暦元)年には許されて都に戻ります。
その際、吉水草庵に入ろうとしましたが、荒れ果てていたため、近くにある大谷禅房(現・知恩院勢至堂)に入っています。
その後、翌年の1月25日に80歳で亡くなりました。
この吉水での法然の布教活動は、流罪となった晩年の数年間を除き、浄土宗を開宗する43歳から生涯を閉じた80歳までの長きにわたり、浄土宗の中心地となりました。
そのため法然の死後、大谷禅房の隣に法然の廟が造られ弟子が守っていましたが、1227(嘉禄3)年、延暦寺の衆徒によって破壊されてしまいました。
しかし、1234(文暦元)年に法然の弟子である紫野門徒の勢観房源智が再興し、四条天皇から「華頂山知恩教院大谷寺」の寺号を下賜されるなどすると、次第に紫野門徒の拠点となっていきました。
 四条天皇
四条天皇
1276(建治2)年、鎮西義の弁長の弟子良忠が鎌倉からやってくると、まもなくして紫野門徒の百万遍知恩寺3世信慧は、東山の赤築地において良忠と談義を行いました。
そこで両流を校合してみたところ、相違するところが全くなく符合したので、以後源智の門流は別流を立てずに、鎮西義に合流することとなりました。
これにより、紫野門徒の拠点であった知恩院と百万遍知恩寺は、鎮西義の京都での有力な拠点となりました。
1431(永享3)年に火災にあって焼失しましたが、その後、再興されました。
 百万遍知恩寺
百万遍知恩寺
1467(応仁元)年に始まった応仁の乱の際には、知恩院22世周誉珠琳が近江国伊香立(現・大津市伊香立)の金蓮寺に避難し、法然御影や仏像、宝物類を付近にあった庵に避難させ、この庵を改めて新知恩院としました。
そして、1478(文明10)年に知恩院を再興しましたが、1517(永正14)年に焼失しました。
1523(大永3)年、知恩院25世超誉存牛(ちょうよぞんぎゅう)と百万遍知恩寺25世慶秀との間で本寺争いとなりましたが、知恩院が勝利し、鎮西義で第一の座次となり本山となりました。
1530(享禄3)年に勢至堂が再興され、後奈良天皇より宸翰と「知恩教院」「大谷寺」の勅額を賜っています。
ちなみに、現存の三門、御影堂(本堂)をはじめとする壮大な伽藍が建設されるのは、江戸時代に入ってからのことです。
つまり、法然の活動より約400~500年ほど経てから、ようやく現在私たちが見ることのできる知恩院の建物が建てられたということです。
浄土宗徒であった徳川家康は1603(慶長8)年に知恩院を永代菩提所と定めて寺領703石余を寄進したうえ、翌1604(慶長9)年からは、北に隣接する青蓮院の地を割いて知恩院の寺地を拡大し、諸堂の造営を行っています。
造営は江戸幕府2代将軍徳川秀忠に引き継がれ、現存の三門は1621(元和7)年に建設されました。
1633(寛永10)年の火災で、三門、経蔵、勢至堂を残しほぼ全焼しましたが、3代将軍徳川家光のもとでただちに再建が進められ、1641(寛永18)年までにほぼ完成しています。
 徳川家康
徳川家康
 徳川秀忠
徳川秀忠
 経蔵
経蔵
 勢至堂
勢至堂
徳川家が知恩院の造営に力を入れたのは、徳川家が浄土宗徒であることや、知恩院25世超誉存牛が松平氏第5代松平長親の弟であること、二条城とともに京都における徳川家の拠点とすること、徳川家の威勢を誇示し、京都御所を見下ろし朝廷を牽制することといった、政治的な背景もあったといわれています。
江戸時代の代々の門主は皇族から任命されましたが、さらにその皇子は徳川将軍家の猶子となっていました。
 二条城
二条城
1710(宝永7)年、それまで勢至堂の前にあった阿弥陀堂を現在地に移しています。
また、霊元上皇より宸翰と「華頂山」の勅額を賜っています。
1947(昭和22)年、知恩院は法然上人御廟を中心とする「一宗一元運動」を提唱すると、12月8日、知恩院は自らを本山とする本派浄土宗(後に浄土宗本派に改称)を結成し、浄土宗から分派します。
1950(昭和25)年には、法然上人御廟の向かいにある一心院が浄土宗捨世派を結成して浄土宗から分派しました。
しかし、1961(昭和36)年の法然上人750年忌を機に、翌1962(昭和37)年に知恩院と浄土宗本派は浄土宗に合流し、知恩院が再び浄土宗の総本山となりました。
2011(平成23)年に御影堂の半解体をともなう大修理を発願し、8年計画で屋根瓦の全面葺き替えをはじめ腐朽、破損箇所の取り替えと補修、軒下の修正、耐震診断調査に基づく構造補強などを行いました。
2019(令和元)年にひとまず竣工し、内装などの復元を行って、2020(令和2)年4月13日に落慶法要が行われました。
一度外されて補修された屋根は、2016(平成28)年に再び御影堂に載せられました。
なお、解体中は月に1回、無料で修理現場が公開され、屋根が戻された直後も修理現場が一般公開されました。
 平成大修理
平成大修理
知恩院の境内は、三門や塔頭寺院のある下段、御影堂(本堂)など中心伽藍のある中段、勢至堂、法然廟などのある上段の3つに分かれています。
このうち、上段が開創当初の寺域であり、中段、下段の大伽藍は江戸時代になって江戸幕府の全面的な援助で新たに造営されたものです。
総門(新門)を通り、緩い坂道を上った先に三門が建っています。
1619(元和5)年9月に徳川秀忠の命で三門と経蔵の造営が始められ、1621(元和7)年秋には、ほぼ完成しました。
平成大修理時に上層屋根の土居葺板という部材から1621(元和7)年の墨書が発見され、同年の建立と判明しました。
形式は五間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺で西面します。
「五間三戸」は正面柱間が5つで、うち中央3間が通路になっているものです。
「二重門」は2階建てで、1階・2階の両方に軒の張りだしがあるものをいいます。
 三門
三門
高さ24メートルの堂々たる門で、東大寺南大門より大きく、現存する日本の寺院の三門(山門)の中で最大の二階二重門です。
組物(軒の出を支える構造材)を密に並べた「詰組」とすること、粽(ちまき)付きの円柱を礎盤上に立てること、上層の垂木を扇垂木とすることなど、細部の様式は禅宗様であり、禅寺の三門に似た形式とします。
門の上層内部は釈迦如来像と十六羅漢像を安置し、天井には龍図を描くなど、やはり禅寺風になっています。
なお、山門ではなく三門と呼ばれていますが、それは、「空門(くうもん)」「無相門(むそうもん)」「無願門(むがんもん)」という悟りに通ずる三つの解脱の境地を表わす門・三解脱門(さんげだつもん)という意味からです。
日本三大門のひとつに数える説がある三門をくぐると「男坂」と呼ばれる急な階段があります。
本堂などの建つ「中段」に至る階段です。
右手にはなだらかな階段「女坂」があります。
 男坂
男坂
御影堂は、本堂、大殿とも呼ばれます。
本堂は、中段に南面して建ちます。
前述したように、1639(寛永16)年に徳川家光によって再建されたものです。
法然ゆかりの吉水草庵があった場所であるとされています。
宗祖法然の像を本尊として安置することから、御影堂(みえいどう)と呼びます。
知恩院で最大の堂宇であることから、大殿(だいでん)とも呼ばれます。
 御影堂
御影堂
 御影堂内部
御影堂内部
入母屋造本瓦葺き、間口44.8メートル、奥行34.5メートルの壮大な建築で、江戸幕府造営の仏堂としての偉容を示しています。
建築様式は外観は保守的な和様を基調としつつ、内部には禅宗様(唐様)の要素を取り入れています。
柱間は桁行(正面)11間、梁間(奥行)9間で、手前の梁間3間分を畳敷きの外陣とし、その奥の桁行5間・梁間5間分を内陣としています。
内陣の左右はそれぞれ手前の梁間3間分を「脇陣」、奥の梁間2間分を「脇壇前」と呼びます。
堂内もっとも奥の梁間1間分は、中央の桁行5間を後陣、左右の桁行各3間を脇壇とします。
内陣の奥には四天柱(4本の柱)を立てて内々陣とし、宮殿(くうでん)形厨子を置き、宗祖法然の木像を安置します。
江戸幕府の造営になる、近世の本格的かつ大規模な仏教建築の代表例であり、日本文化に多大な影響を与えてきた浄土宗の本山寺院の建築としての文化史的意義も高いことから、2002(平成14)年に三門とともに国宝に指定されています。
ここでは書ききれないですが、知恩院は他にもまだまだ見所や建物がありすので、訪れた際にいろいろと見て回ってみてください。